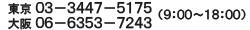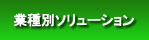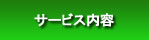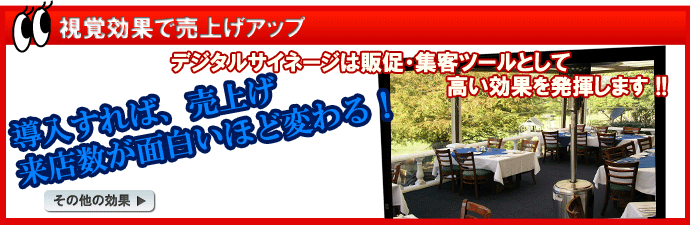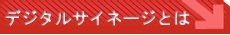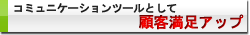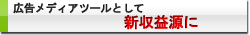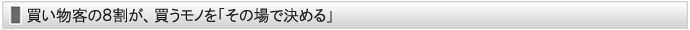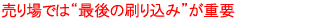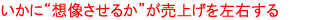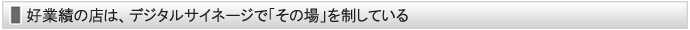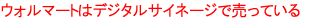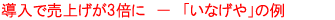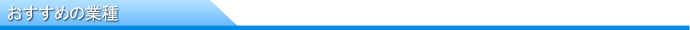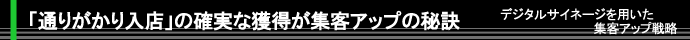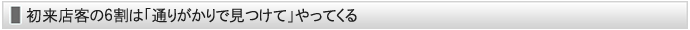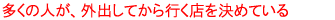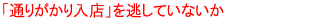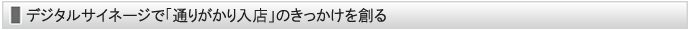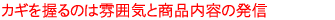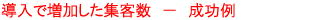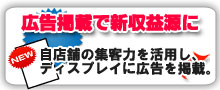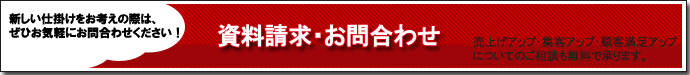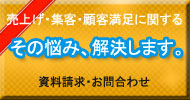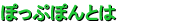【このページ内でのリンク】 販売促進ツールとしての活用と効果 集客ツールとしての活用と効果
諸調査機関によると、買物客の8割は、何を買うかを「店に入ってから決めている」と発表されています。
また、消費者心理として「直前に影響を受けたものを買う」という分析結果もあります。
つまり買物客の多くは、明確な目的がない限り、「その場で、たまたま興味をひかれたもの」を買うわけです。
これは逆に店側からみると、売り場での“最後の刷り込み”の成否が、商品の売れ行きを決めているということです。
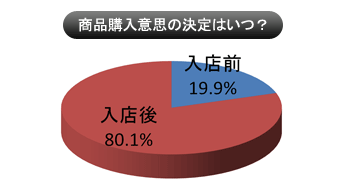
“想像”は人の消費活動に大きく関わっています。特に、具体的なシーンの想像は非常に大きな影響を与えています。
例えば、餃子とビールを別々に売るより、セットで売った方が売上げが伸びます。
これは、「餃子を食べながらビールを一杯やる」というシーンが、それぞれを単品で食するシーンよりも、よりリアルで魅力的に想像できるからです。
このように、商品を組合わせるなどして、その利用シーンや楽しみ方をリアルに想像させることは、消費者の購買意欲を強く刺激する効果があります。
売り場でいかに“想像させるか”が重要なのです。
上記の通り、売り場において、インパクトが強く、またリアルな想像を誘因する情報の提供は非常に効果的です。
そのために、デジタルサイネージは最適なツールです。
世界最大の小売業であるウォルマートストアーズは、デジタルサイネージを積極的に導入している企業の代表格で、店内販促利用の先駆けです。
同社によれば、特定商品のデジタルサイネージを見た顧客の15%がその商品を購入しており、
月間約4万〜30万ドルの売上げ増要因となっているそうです。

日本でも、小売業をはじめとして、デジタルサイネージを利用する例が増えてきています。
最近では、数百台規模での大規模な導入を決定する企業も出てくるなど、普及がより一層加速するとみられています。
スーパーマーケットチェーンを展開する「いなげや」は、首都圏の30店舗で254台のデジタルサイネージを導入し、商品広告や料理レシピの配信を行なうことを発表しました。
事前に行なった実証実験の結果では、デジタルサイネージで販促を行なった調味料の売上げが3倍になるなど、高い効果を発揮したとの報告があります。
販促ツールとして、デジタルサイネージの利用が効果的な業種です。
新規顧客の獲得は、店舗の集客に関する永遠の課題です。しかし、新規顧客はどこからやってくるのでしょうか。
情報誌や広告から、なのでしょうか?
実は、アンケート調査によると全体で約5割、男性では6割もの人が「通りがかりに見つけて」入店した、と答えています。
確かに、街に出かける際、事前に行く店を全て決めている人は少数派です。
大抵、2〜3店をピックアップしておいて、後は色々寄り道する・・というケースがほとんどです。
多くの人が外出時、入る店をその場で決めているのです。
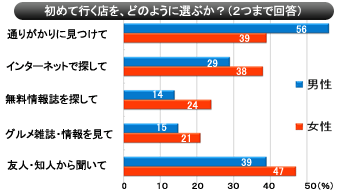
上記の数字から考えると新規顧客の獲得において、「通りがかり入店」は無視できない重要な要素であることがわかります。
もちろん、広告メディア等による販促活動も集客インパクトが大きいですが、その都度費用がかかるケースがほとんどです。
一方、「通りがかり入店」は地道ですが、費用がかからない分、利益率の高い集客ルートと言えるでしょう。
偶然性と単発性が高く感じられますが、逆にこれを必然性と恒常性の高い手法として確立することができれば、
店舗運営上の大きな武器となります。
店の玄関口で、一見客に「ちょっとのぞいてみよう」と思ってもらえるかどうか。
そのための具体的な仕掛けがないかぎり、その店は「通りがかり入店」という貴重なチャンスをみすみす逃しているのです。
店の入口でいかに興味をひく演出ができるか。そのために、デジタルサイネージは最適なツールであると言えます。
あるアンケート調査によれば、新規客の来店動機は、58%が「店内の雰囲気・商品」で、実に半数以上を占めます。
これは見方を変えると、店内の雰囲気と商品のアピールに
成功すれば、通りがかり客が迷わず入ってくれる動機になることを示しています。
玄関口でディスプレイを使い、リアルな店内風景と商品を流すことで、強い集客力を生み出せるのです。

実際に、デジタルサイネージを導入することで、高い効果を得ている例も数多くあります。
福岡県のある飲食店では、デジタルサイネージを看板として導入した結果、新規顧客の集客が伸び、
設置後3ヵ月の平均売上げ高がそれまでの123%にアップしたとの報告があります。
また、来店客からは「映像で入りやすかった」「看板の映像をみて入ってきた」との声が多数寄せられている模様で、
この例では導入が狙い通りの成功をおさめた、と言えるでしょう。
集客ツールとして、デジタルサイネージの利用が効果的な業種です。
↑このページの先頭へ戻る